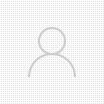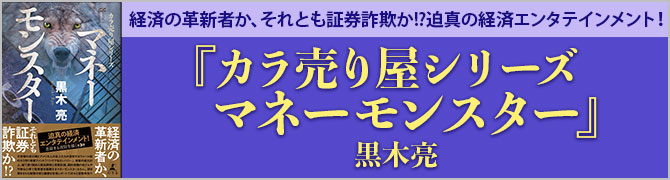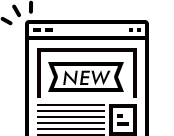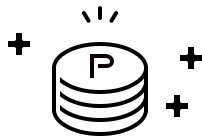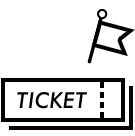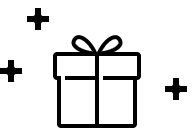忘れられない恋を誰かに語りたくなることがありませんか? その相手にバー店主は時々選ばれるようです。バー店主がカウンターで語られた恋を書き留めた小説『恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。』より、今週のお話。
* * *
ある時、外国人同士のお客様がカウンターで「日本の六月はレイニー・シーズンだからね。雨の京都や鎌倉はとても綺麗だよ」という話をしていたことがある。
なるほど、梅雨のことを彼らはレイニー・シーズンと呼ぶのだ。雨の季節は心が少しだけ重たくなるが、雨が降る街はとても美しい。その夜も渋谷に雨が降っていた。
雨が降る空気が少し湿った夜にはどんな曲があうかしばらく考えてみて、『オール・ザ・シングス・ユー・アー』という曲を思いついた。
「いつの日か僕の幸せな腕があなたを抱きしめる。あなたのすべてが僕のものとなるその時を」という意味の曲だ。
この曲の主人公は実は片思いだ。かなり一方的な片思いだけど、なぜか本人は「いつかあなたのすべてが僕のものとなる」と確信を持っている力強い恋の歌だ。
私は、エラ・フィッツジェラルドのレコードを取り出した。エラが歌うと、恋する熱い気持ちがこちらの心に響いてくる。いつの日か、自分のこの腕があなたを抱きしめるという、熱い気持ちが。
レコードをターンテーブルの上に置いて針をのせると、バーの扉が開いて、男女二人組が傘を畳みながら入ってきた。
男性の方は二十七、八歳。細身でジャケットにTシャツにリュックとカジュアルながら、清潔感がある。勤め人独特の疲れた感じはなく、知的でどこか浮き世離れした雰囲気もあるので、おそらく研究者か学芸員なのではないかと私は想像した。
女性の方は三十四、五歳くらいだろうか。ショートブーツに細身のジーンズ。薄手のグレーのニットに白いストールをふんわりと巻いている。色白で、彼女も知的な雰囲気だ。
女性の方が慣れてるようで、彼女が「ここいいですか?」と言い、二人でカウンターの真ん中に座った。
「タンカレーでジントニックを」と、彼女がメニューを見ずに言うと、男性も「じゃあ僕も同じものを」と注文した。
「ここのジントニックすごくおいしいのよ」彼女が彼に言う。
「でもマスター、タンカレーのジントニックでしたら、どのバーでも同じ味のはずですよね。何かおいしくするコツがあるんですか?」
彼の質問に、私はこう答えた。
「ある広告代理店が『おいしいとなぜ感じるのか』というのを調査したらしいんです。
人が『おいしい』と感じる理由には、『①本来のおいしさ』と『②その食べ物や飲み物が持っているブランドイメージ』と『③それを味わう時の雰囲気』の三つがあると判明したそうです。
一つ目の、本当に味そのものから感じる『おいしさ』はおいしい全体の三割なのだそうです。
二つ目の『ブランドイメージ』ですが、例えばタンカレーというジンは癖がない透き通った味わいで、カクテルとの相性がとても良く、といった物語が、人がおいしく感じる全体の三割だそうです。
残りのおいしいの四割が三つ目の『雰囲気』で決定されるそうです。自宅でまったく同じようにジントニックを作ってもそんなにおいしくないのは、自宅ではバーの非日常的な雰囲気がないからです。一緒に飲んでいる人も関係します。喧嘩をすると『まずくなる』ってよく言いますよね。あれは本当にまずくなるんです。お互いが好きあっていると本当においしくなります」
「なるほど。面白いですね。人間の味覚ってそんなものなんですね」と彼が答えた。
私は二人の前にタンカレーのジントニックを置く。
二人は「乾杯」と言って、ジントニックに口をつける。
同時に「おいしい」と声をもらし、二人は目をあわせ少しだけ笑った。
私は邪魔をしてはいけないと思い、次にかけるべきレコードを思案しているようなフリをした。
彼女が彼に「うちの雑誌、あの女優の件で大忙しで、頂いていた原稿、まだ掲載できなくてすいませんね」なんて話を始めた。
彼が突然、彼女にこう言った。
「いえ、僕の原稿のことなんてどうだっていいんです。そんなことより僕、中島さんに伝えたいことがあるんです。僕、中島さんのこと好きです。お会いした時からずっと好きでした。もうこの気持ちは抑えられなくて今日こそ伝えようと思ってました。大好きです」
私は冷静にレコードのレーベルの曲名をチェックするフリをしながら、心の中では「突然そんな告白してしまって大丈夫なのだろうか」と、あせってしまった。
意外と彼女の方は落ち着いてて、「何言ってるんですか。私に彼氏いるの知ってますよね。もう四年も一緒に住んでるの」と、すぐに答えた。
おそらく、彼女はとっくの昔から彼が自分に気があるとわかっていて「今日あたり彼が自分に告白するだろうな」と、薄々予想していたのだろう。
彼がこう言った。
「知ってます。フェイスブックで顔も見ました。感じの良さそうな人でした」
「でしょ。彼とはすごく仲が良くて、そろそろ結婚もしそうなんです」
「でも、僕、中島さんのこと、すごく好きです。彼が中島さんのことを好きなのよりも絶対にもっともっと好きな自信があります」
「何言ってるんですか」
「僕、中島さんが彼と別れるの待ちます」
「あのですねえ……」
「あの……、中島さんも、僕のこと好きですよね」
「ええ?」
「あ、やっぱりそうですよね。じゃあ僕、これから中島さんのこと、一生懸命口説きます。デートとかも彼よりもすごく楽しいものにします。おいしいお店とか勉強します。中島さん、絶対に僕といる方が幸せになると思います」
「ちょっと何を突然勝手に言い出してるんですか。そんなのありえないですから」
「すいません。でも僕、本気です。今日はこれでこの話終わりにします。でも、本気で中島さんのこと好きです」
ここで二人はこの件についての話を終え、また仕事の話に戻った。
しかし、明らかに空気がその彼の告白の前と後とで「ふっ」と変わってしまったのを私は感じとった。彼は明らかに彼女のことを真剣に見つめる「男」になったし、彼女もその視線を意識してしまって、会話も以前のように弾まなくなった。
彼女がもてあましたかのように、私に「マスター、このジントニックやっぱりおいしいですね」と言った。
すると彼は「好きな人と飲むとおいしく感じるとさっきマスターが言ってましたよ」と言う。彼女は彼の方を見ないで、私に「もう一杯同じものを」と注文した。
後ろではエラ・フィッツジェラルドが「いつの日か私の腕があなたを抱きしめる。あなたのすべてを」と歌っていた。
* * *
続きは、『恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。』をご覧ください。
恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる

- バックナンバー
-
- エゴサーチはしない“脱・恋愛の教祖”とエ...
- 「ミュージシャンはどんな出会いが多い?」...
- 文庫解説をnoteで募集いたします #恋...
- 四十歳の女性と二十五歳の男性の恋はうまく...
- これは完全に片想い【再掲】
- 連れ去られるような出会い【再掲】
- 女優の同級生と少しずつ仲良くなったけれど...
- 私を月に連れてって【再掲】
- 恋には季節がある【再掲】
- 恋に落ちた日(サカエ コウ。)#ファース...
- 手を繋ぐ記憶と(ぴぴぷる) #ファースト...
- あの夏の指先(ふみぐら社) #ファースト...
- 誰かを誘うきっかけづくりのためのセット商...
- 何も始まらずに終わった恋
- 美術部の教え子の彼女が好きだった
- 好きだという気持ちを絶対に知られたくない
- バンドマンとの恋が成就するとき
- 一年間だけと決めた既婚者同士の恋
- バー初心者でも怖くない!東京トップバーを...
- 会うための口実がやっといらなくなったのに
- もっと見る