
軍歌は戦時中の生活に根差した大衆の娯楽であった。「音楽は軍需品なり」。一人歩きしたこの言葉の通り、音楽業界は総力戦体制に飲み込まれていく。1940年代、「軍歌大国」日本は引き返せないところまで来ていたのだ。『日本の軍歌』からの抜粋でお送りするシリーズ最終回は、歌から聞こえてくる敗戦間際の断末魔の叫びです。
「決戦歌曲」という断末魔の叫び
一九四四(昭和十九)年十月、「神風特別攻撃隊」の出撃が報じられると、軍歌にも「神風」ならぬ「神曲」を求める声が高まった。そんな中で、同年十一月に「神鷲を穢す歌曲」、翌年三月に「神曲出でよ」と「駄曲」批判の投書が相次いだ(「朝日新聞」)。
これに応えるように、一九四五(昭和二十)年四月、『音楽文化』は「決戦歌曲特集号」、『音楽知識』は「決戦ハーモニカ音楽特集号」を刊行した。本来は一月に刊行予定だったものの、空襲により四月にずれ込んだという。
作曲家の小松耕輔は「決戦歌曲特集号」の序文で、神風特別攻撃隊の「神州不滅、皇国必勝の信念」をもって、音楽家は軍歌を作曲しなければならないと訴えている。あれだけ隆盛を極めた戦前日本の音楽雑誌の、これが最後の姿だった。
「決戦歌曲」はわずか二三曲にすぎない。定番の「海ゆかば」と「愛国行進曲」をはじめ、「婦人従軍歌」「空の神兵」「ラバウル海軍航空隊」「加藤部隊歌」「燃ゆる大空」「大航空の歌」「若鷲の歌」「愛国の花」「暁に祈る」など既出の軍歌が並ぶ。
一方で、「迫る鬼畜の米英を、太平洋に叩き込め」と叫ぶ、大政翼賛会撰定の「突撃喇叭鳴り渡る」(勝承夫作詞、古関裕而作曲)は、大戦末期の悲惨な軍歌をよく現している。映画主題歌「勝利の日まで」はまだしも、学徒動員の歌「あゝ紅の血は燃ゆる」や、陸軍特別幹部候補生の歌「特幹の歌」などは、苦しい台所事情を告白しているようなものだ。また「台湾沖の凱歌」は、大本営発表の虚報に踊らされて「五十八機動部隊殲滅だみよや」と喜ぶ歌で見ていて痛々しい。
その中でも目を引くのがやはり「嗚呼神風特別攻撃隊」(野村俊夫作詞、古関裕而作曲)だろう。「神風」の軍歌としては、最もよく知られたものである。
無念の歯がみ怺(こら)へつゝ 待ちに待つたる決戦ぞ
今こそ敵を屠らむと
奮ひ起ちたる若桜!
大義の血潮 頬そめて
必死 必中 体当り
敵艦などて逃すべき
見よや不滅の大戦果!
(全六番のうち一、四番)
「決戦歌曲」というよりも、もはや「断末魔の叫び」といったほうがふさわしい。ここまで過酷な文言が世を被ったのは、日本の文学史上でも稀なことではなかっただろうか。
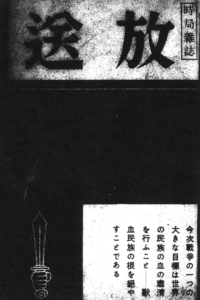
口伝えで広まった軍歌、「同期の桜」
「決戦歌曲特集号」の刊行準備が進められていた一九四五(昭和二十)年二月半ば、マニラ東部の山麓地帯(「神州要塞」と呼ばれた)に立てこもる振武(しんぶ)集団で「神州毎日」という新聞が創刊された。名前からもわかるように、「毎日新聞」の社員たちによって編集された陣中新聞だった。
「神州毎日」はその創刊記念として、なんと「神州要塞の歌」という軍歌を懸賞募集した。賞品は清酒一升。編集員たちには軍歌募集の雄「毎日新聞」社員としての自負があったのだろうか。激戦下のフィリピンでさえ軍歌が募集されたのは大変興味深い。
「神州要塞の歌」は、学徒動員された黒木政春という陸軍少尉の応募作「斬りこみ隊の歌」が当選。それに音楽に心得のある兵隊が作曲して、軍司令部前の広場で盛大な発表会が開かれたという。
このようにレコード化されなかった軍歌は、どうしても歴史に埋もれてしまいがちである。しかし、大手メディアを介さずに作られた軍歌として、これらも見逃すことができない。戦後の戦友会への聞き取り調査でも、替え歌は上位にランクインしている。
その一つに「ラバウル小唄」がある。この軍歌は、一九四〇(昭和十五)年に発売された「南洋航路」(若杉雄三郎作詞、島口駒夫作曲)の替え歌で、戦争後半に口伝で広まったといわれる。驚くべきことは、この軍歌が金正日(キムジョンイル)の愛唱歌だったということだ。「金正日の料理人」だった藤本健二によれば、金正日は「ラバウル小唄」を宴会で朝鮮人民軍の幹部と共に歌っていたらしい。スカルノの愛唱歌となった「愛国の花」といい、日本軍歌がかつて持っていた伝播力には目を見張るものがある。
ただ、太平洋戦争の替え歌軍歌としては、やはり「同期の桜」を挙げなければならない。これは前章で紹介した「二輪の桜」(西条八十作詞、大村能章作曲)の替え歌である。
一九三九(昭和十四)年頃、海軍兵学校七十一期の帖佐裕が江田島の「金本クラブ」で「二輪の桜」のレコードを聴き、替え歌にしたのがその始まりだった。その後、帖佐と同じ海兵七十一期の一部と、戦争末期の海軍潜水学校を中心に「同期の桜」は広まり、歌詞も書き加えられていったという。
貴様と俺とは 同期の桜 同じ兵学校の 庭に咲く
咲いた花なら 散るのは覚悟 みごと散りませう 国のため
(一番)
西条の「君と僕」とは異なり、現役軍人の替え歌は豪快だ。現在伝わるもののうち、一、二、五番は帖佐が作詞したものだが、三、四番は別人の手になるといわれる。
特に次の三番は、オリジナルの作詞者・西条八十も「替え歌ながらうまいもんだ」と褒めたらしい。
貴様と俺とは 同期の桜 同じ航空隊の 庭に咲く
仰いだ夕焼け 南の空に 未だ還らぬ一番機
「露営の歌」にせよ、「暁に祈る」にせよ、このような「兵隊目線」の軍歌が当時比較的ヒットに恵まれた。だから西条の賛辞も腑に落ちるものがある。
日本洋楽史のバッドエンド、「米英撃滅の歌」
さて、本章もそろそろ終わりに近づいてきた。それは軍歌の歴史が終わりに近づいていることをも同時に意味する。そこで私は日本軍歌の締めくくりとして、「米英撃滅の歌」という軍歌を挙げたいと思う。
数多ある日本軍歌の中で、なぜ「米英撃滅の歌」が締めくくりにふさわしいのだろうか。それは、この軍歌の中に明治以来の洋楽移入の歴史が端的にまとめられていると思われるからである。
その説明のためには、「米英撃滅の歌」を主題歌とする、松竹映画『撃滅の歌』の内容を見なければならない。
戦災によってレコードの生産が中止に追い込まれていた一九四五(昭和二十)年三月、一本の映画が封切られた。その名は『撃滅の歌』。一九三九(昭和十四)年音楽学校を卒業した三人の女性が、太平洋戦争の激化に当たって再び集まり、恩師と共に「米英撃滅の歌」を歌う、というのがその内容だ。
ここで三人の女性は、日本の洋楽ジャンルをそれぞれ象徴している。
まず、ジャズ音楽家の萩原と結婚し、上海に渡った桜井千鶴(高峰三枝子)は「ジャズ」。次に、新進の作曲家の小牧と結婚し、田園調布に暮らす堀越弓子(轟夕起子)は「高級音楽」。最後に、軍楽隊員の川上を親戚に持ち、郷里の奈良に帰って小学校の唱歌教師になった下田美恵(月丘夢路)は学校や軍隊などの「実用音楽」。
こうしてそれぞれ別の道に進んだ彼女たちだったが、戦争の暗い影はその上にも覆いかぶさった。一番悲劇的なのは「ジャズ」を象徴する千鶴だろう。上海で米国の放った刺客に夫を殺害され失意のうちに帰国。「紀元二千六百年」が歌われる奈良の小学校で美恵と再会し、「ジャズはアメリカの文化謀略」と気づいたと嘆くのだった。
その後、弓子の夫・小牧が友人の川上の戦死をきっかけに「米英撃滅の歌」を作曲。再び東京に結集した三人の女性は、かつての恩師・藤原義江(本人役)と共にこの「米英撃滅の歌」を歌って出陣学徒や労働者を励ますのだった。
こうして、「ジャズ」「高級音楽」「実用音楽」と多様化した筈の日本の洋楽は、再び「米英撃滅の歌」という軍歌にまとめられてしまった。これは堀内敬三や山田耕筰など各分野で活躍していた音楽家たちが、結局は戦争で軍歌の制作に引きずり込まれたことを図らずも戯画化しているといえないだろうか。
またもう一つ注目すべきなのが、「米英撃滅の歌」に関わった三人の男性である。劇中では弓子の夫が作曲したということになっているが、実際には山田耕筰が作曲を担当した。山田はかつてカーネギーホールのコンサートを成功させ、米国とは浅からぬ縁があった。一方、作詞者は十年以上米英で生活し、その英語詩が高く評価された詩人のヨネ・ノグチこと野口米次郎。野口もまた米国に少なからぬ恩義のある国際派だった。
そして恩師役の藤原義江は、すでに述べたようにスコットランド人とのハーフ。すなわち、この三人の男性は世が世ならば、国境を超えて芸術を創造しうる筈だった。にもかかわらず、彼らが集まってできたのが「米英撃滅の歌」だったという不運。
まさに「米英撃滅の歌」は、日本洋楽史のバッドエンドであった。
濤(なみ)は哮る 撃滅の時は今だ 空母戦艦 断じて屠れ
海が彼奴らの 墓場だ 塚だ 海が彼奴らの 墓場だ 塚だ
風は咆える 覆滅の時は今だ 魔翼 妖鳥 断じて墜とせ
雲が彼奴らの 経帷子だ 雲が彼奴らの 経帷子だ
草は燃える 殲滅の時は今だ 鬼畜米英 断じて斃(たお)せ
山が彼奴らの 墓標だ墓石(いし)だ 山が彼奴らの 墓標だ墓石だ
時は今だ 決勝の時は今だ 興亜聖戦 断じて遂げよ
み民われらの 命が的だ み民われらの 命が的だ
明治時代、軍隊と学校と宮廷で導入された洋楽は、日清・日露戦争でエンタメとして国民の間に定着した。明治末から大正にかけての平和な時代に、洋楽は大衆音楽や高級音楽となり国民に広く消費された。しかし、そうした音楽大国は日中戦争の深まりと同時に「軍歌大国」へと変貌してしまった。その締めくくりとして、この「米英撃滅の歌」ほどふさわしい軍歌は他にないと私は思うのである。
国民的エンターテインメントの末路
その最後は悲惨だった。「軍需品」のように軍歌を生産し続けた「軍歌大国」という利益共同体は、敗退に敗退を重ねる帝国日本と運命を共にし、「一億特攻」と「米英撃滅」という断末魔の叫びを上げながら瓦解した。日清戦争以来、国民的なエンタメとして消費され続けた軍歌は、こうして大きな損失と多くの戦死者を後に残したのだった。
終戦間近の八月五日、ある軍歌が懸賞募集された。主催は日本音楽文化協会、日本放送協会、「朝日新聞」「毎日新聞」「読売報知」そして全国の地方紙。後援にはかつて「愛国行進曲」を募集した内閣情報部の後身、情報局がついた。もはやメディア間の競争どころではなかった。「本土決戦」のためのこの軍歌には、戦時のインフレもあったとはいえ、作詞・作曲ともに破格の五〇〇〇円の賞金が用意された。
その締切りの日は奇しくも八月十五日だった。過酷な状況にもかかわらず、応募数は一万五二〇六篇(うち作曲二六四篇)に達したという。未発表に終わったこの軍歌のタイトルは、「国民の軍歌」であった。
一八八五(明治十八)年の「軍歌」(来れや来れ)に始まった「国民の軍歌」の歴史は、かくして終わった。およそ六十年。推定だが、この間に作られた軍歌の数は一万曲を下らないだろう。



















